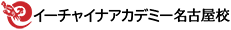たびたび子どもの外国語の習得の速さとその精度に驚いたことはありませんか?
子どもの発音を聞いてみると、驚くほどネイティブに近い発音をしています。外国語を学ぶ多くの人の最難関とも言える「発音」を、なんなくクリアしていく子どもたちを見て、羨ましいばかり・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なぜ子どもたちはネイティブのような発音ができるのでしょうか?
その理由の1つは言語学習の「臨界期」があるからです。
0歳~12歳までの幼年期・少年期は、言語習得の黄金期であると言われます。人間が言葉を習得するのに、この時期の言語環境が非常に大きな影響をもっているということです。またその時期を過ぎると急速に言語習得能力が衰えていくとも言われています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
子どもは外国語をスポンジのように吸収し、すぐにマスターしてしまいます。
そこでわたしたち大人は、子どもたちから外国語の習得のコツを学ぶことができます。それは子どものように純粋に・素直に聞いたことを真似し、そのまま声に出すこと。そして繰り返し何度も聞いて、読む練習をすれば、ネイティブのように綺麗な発音も夢ではありません。
これからの「切磋琢磨の館」の中に、中国の2500年前の偉大な思想・哲学・教育家である孔子の『論語』に記載された「弟子規 聖人訓 首孝弟 次謹信 泛愛衆 而親仁 行有余力 則以学文」の文、中国清朝の康煕年間の李毓秀によって書かれた『訓蒙文』、そして全108条の基本規則、360文、1080文字があり、3文字で1句とし韻を踏んでいる《弟子規》を使用して、中国の伝統文化を学習しながら発音を練習していきたいと思います。
今後毎週金曜日に《弟子規》の『中国語発音、中国語簡体字、中国語繁体字、中国語解釈、日本語訳、』の5つの内容で皆さんに発信します。中国文化が好きな方、中国語の発音をきれいにしたい方は是非一緒に頑張りましょう!
---------------------------------
《弟子規》—総序
1. 中国語音声
********************************************************************************
2. 中国語(簡体字)
********************************************************************************
zǒng xù
<总 叙>
dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
泛爱众 而亲仁 有余力 则学文
********************************************************************************
3. 中国語(繁体字)
********************************************************************************
<總 序>
弟子規 聖人訓 首孝悌 次謹信
泛愛眾 而親仁 有餘力 則學文
********************************************************************************
4. 中国語解釈
********************************************************************************
弟子规这本书,是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。首先在日常生活中,要做到孝顺父母,友爱兄弟姊妹。其次在一切日常生活言语行为中要小心谨慎,要讲信用。和大众相处时要平等博爱,并且亲近有仁德的人,向他学习,这些都是很重要非做不可的事,如果做了之后,还有多余的时间精力,就应该好好的学习六艺等其他有益的学问。
◆◆◆ 【 弟子规 圣人训 首孝弟(同‘悌’) 次谨信】◆◆◆
【解释】弟子规,是圣人的教诲。首先要孝敬父母、友爱兄弟姊妹,其次要谨言慎行、讲求信用。
◆◆◆ 【泛爱众 而亲仁 有余力 则学文】◆◆◆
【解释】博爱大众,亲近有仁德的人。 有多余的时间和精力,学习有益的学问。
5. 日本語訳
********************************************************************************
『弟子規』は聖人賢者の教訓である。先ず日常生活の中で親孝行をし、兄弟姉妹と仲良くする。 その次に日常生活のすべてに渡って言動を慎み深くする。人と接するときは思いやりを持ち、仁徳のある人に近づいて学ぶ。さらに時間と気力があれば、有益な学問をすべきである。